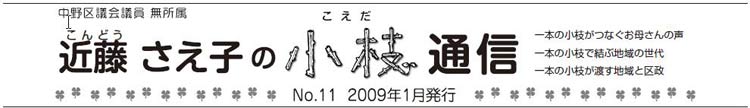
小枝通信NO.11 2009年1月発行
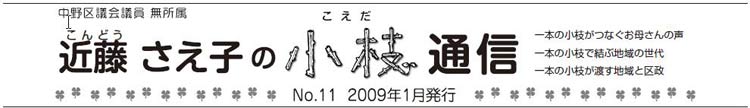
 2009年 新しい年が始まりました。 2009年 新しい年が始まりました。「100年に一度の世界的経済危機」と言われる不況下で、国民の生活は厳しくなる一方です。 経営に行き詰まった企業は、非正規雇用者を次々打ち切ります。突然の「解雇」に戸惑う労働者とその家族。しかし今のこの状況は、これまで日本が企業利益優先、経済優先でやってきた結果です。派遣等の非正規雇用を促進する法律も、私たちが選んだ国会の議決で決まったものです。今年は2006年改正労働者派遣法で定められた派遣労働の「最長3年」の切れ目の年でもあり、雇用問題はさらに深刻化する可能性があります。 私たちは自分が厳しい状況に置かれて初めて「これではいけない」と気づきます。この「100年に一度の危機」が、本当に人間らしく生きられる社会を目指すための「気づき」につながる「チャンス」となることを願います。 皆様にとって、明るい年になりますことを願ってやみません。今年もよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
|
 ◆区が中野サンプラザの株式取得 ◆区が中野サンプラザの株式取得10月24日、平成20年度中野区議会第三回定例会において以下のとおり補正予算が可決されました。 1、中野サンプラザの運営会社である (株)中野サンプラザ が所有する(株)まちづくり中野21 の普通株式2000株、およびC種優先株1株を9億7千万円で区が取得する。 2、 (株)中野サンプラザ が、サンプラザを運営するために必要な資産(人材を含む)を移した子会社(新運営会社)を設立、これを取得するために4億5百万円を出資する。 当初から「区のサンプラザ取得に反対する」立場を明らかにして議員になった私は、上記予算に反対しましたが、自民(14)、公明(9)、国民新党(1)、無所属(1)計25人の賛成多数で決定しました。 そもそもサンプラザは国の不採算事業でした。中野区は、「サンプラザは将来の『にぎわいの街づくり』に欠かせない」の1点張りで、「お金はないが、欲しい物は欲しい」とでも言うように、4年前、サンプラザを取得する第三セクター「(株)まちづくり中野」の立ち上げに2億円出資しました。この時、田中区長は、「2億円以上の税金の投入は ない」と明言されました。たった4年で「最初の枠組みがうまく行かなくなった」と言って、区民に対する約束を反故にすることが決まったのです。  今回、サンプラザ運営会社の筆頭である(株)BBH(旧ビジネスバンクコンサルティング)のサンプラザ運営から撤退したいという申し出を受け、中野区は、運営会社の責任を問うこともせず、世界的に株価が暴落している今2億円の「配当」をつけて株を買い取ることに決めました。 私は、「区民との約束を、説明もなく変更するのはおかしいのではないか。『4年前より少しお金ができた』と言って、区民に充分な説明もなく、サンプラザの株取得に税金を使う事に反対する。『まちづくり計画』は4年経った今も青写真さえ提示されていない。区民の生活が切実な時、『絵にさえも描かれていない餅』より、身近な生活を少しでも良くする事を区民は望んでいる」と反対の討論をしました。 今回の議案は、一般質問も総括質問も終わってからの本会議への上程でした。区民がこの議案を知ってから10日あまりという短い時間で、13億円以上の出資は決定しました。 |
|
|
|
|
| 税金を無駄にしても ◆反省のない中野区「区民に対し申しわけなくは思わない」  10月6日第三回定例会で、私 近藤さえ子は「上野原スポーツ施設」についての総括質疑をしました。この総括をするにあたり、私は感慨深い思いでした。なぜなら、18年前(1990年)に「上野原スポーツ施設建設」が議案となった時から、私の父
近藤正二を初め、生活者ネットワークの村守恵子元議員、故 藤本泰民議員らが「買ってはいけない」と強く反対したにもかかわらず購入された土地だったからです。1994年、議会の圧倒多数の賛成で購入されましたが、計画は頓挫し、土地は使われる事なく維持されてきました。今回、区はこの20haの土地を山梨県上野原市に売却しました。「スポーツ施設建設のために」という話が出てから実に18年、巨額の損金を出しての「処分」でした。 10月6日第三回定例会で、私 近藤さえ子は「上野原スポーツ施設」についての総括質疑をしました。この総括をするにあたり、私は感慨深い思いでした。なぜなら、18年前(1990年)に「上野原スポーツ施設建設」が議案となった時から、私の父
近藤正二を初め、生活者ネットワークの村守恵子元議員、故 藤本泰民議員らが「買ってはいけない」と強く反対したにもかかわらず購入された土地だったからです。1994年、議会の圧倒多数の賛成で購入されましたが、計画は頓挫し、土地は使われる事なく維持されてきました。今回、区はこの20haの土地を山梨県上野原市に売却しました。「スポーツ施設建設のために」という話が出てから実に18年、巨額の損金を出しての「処分」でした。18年という歳月は、すぐに思い出せないほど長いものです。「当時はバブルだったから」「経済の変化は予測できなかった」と言う人もいます。しかし、この土地購入はバブル心理に乗じて行われたものではありません。購入までに4年という歳月をかけ、その間、地価は明らかに下がり、持ち主の暴力団との絡みが指摘され、購入に反対する議員による予算修正動議まで提出されたにもかかわらず、「区民がスポーツ施設を求めているから」の1点で、一度動き出した計画は止められないとでも言うように、財政的に厳しかった中野区が借金して購入した土地なのです。 今回、上野原の土地の売却が明らかになって以降、区民が集まる説明会に私と共に出向いた近藤正二は「私はできる限りの事をして反対しましたが、結局皆さんの税金を無駄にする結果となり、力及ばず申し訳ない」と区民に頭を下げました。区民のためを思い長年頑張ってきたにも関わらず、購入を阻止できず区民に詫びることになった無念な気持ちがよくわかり、その父の姿に、一人の議員として多くのことを学ばせてもらいました。 一方、区側は「目的が果たせず残念だが、議会で決めた事であり、当時の判断は間違っていなかった」と「残念」の一言で締めくくりました。 本当に「残念」だったのは、誰でしょうか。言うまでもなく、多額の税金を託した事業に頓挫されてしまい、代替のスポーツ施設の一つも持てなかった区民です。「新しいスポーツ施設」の夢を踏みにじられ、「負の資産」に税金をつぎ込まれ、新しい夢を持てなかった区民です。 「税金を無駄に使い、区民に申し訳ないと思わないのか」と私は質問しましたが、「議会で決めた事だから思わない」という答弁でした。 「まずかった事」「反省すべき事」であっても、その結果に真摯に向き合い、事実に基づいた検証をしなくては意味がなく、また同じ事を繰り返す可能性もあります。今回の中野サンプラザが、この上野原の二の舞にならないことを祈るばかりです。 「議会で決めた事」だから「絶対」である。「これが民主主義の本質だ」。であるのなら、区民の皆さんに、議員を選ぶことの大切さを、もっともっと考えていただくほか、できることはないのかもしれません。 |
|
|
|
|
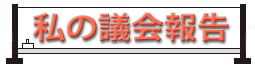 私の議会報告 ●議会質問● 中野区議会本会議および決算特別委員会総括質疑において、 近藤さえ子は以下の質問をしました。 短縮にあたり文章に少し手を加えてあります。全文は近藤さえ子の小枝ネット「私の議会活動報告」に掲載中です。 |
|
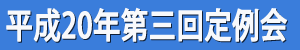 |
|
|
2008年9月26日 一般質問 ●中野区政策研究機構について 区が新たに設立した「中野区政策研究機構」の調査結果が出たが、過去の調査の引用が多く、果たして調査研究の必要性があるのか。ただ、中野区は23区内でも75歳以上の高齢者の一人暮らし世帯が多く、3番目の低就業率であること、コミュ二ティや共同性に対する意識が低く『個人意識』が非常に強い事がわかったこと等、現在の中野区の問題点や課題が浮き彫りになった点は評価できる。特に、高齢者の経済生活や介護、防犯や防災などの問題が深刻化する可能性を示している。また高齢福祉施策は善意の区民ボランティアだけではとても間に合わないことが明らかになった。 中野区は「調査」はするが、「実行」が伴わない。今回の調査結果を受け、それらの課題や問題を速やかに解決していく「実行部隊」をすぐに構成するべきである。 ●副区長3人制について 副区長が3人いるのは23区で中野区だけである。区は職員2000人体制の「小さな政府」を築く方針であり、公益活動を担う多くの「自治意識を持つ区民」が無償である今、高給の特別職が多いことに矛盾はないか。3人の副区長は多すぎると感じる。 しかし、すでに3人の副区長を置いた状況で考えると、地方自治法に元づき、副区長の専門性を生かしスピーディな政策決定が出来るよう、区長の権限を委任していくべきではないか。 部長を置かず副区長が兼務することにメリットは感じられず、「副区長が部長職もこなすため、決裁等が遅くなり仕事がスピーディに捗らない。混乱がある。」と職員の声も聞く。 2008年10月6日 決算特別委員会 総括質疑 ●上野原問題について 6月の議会で売却が決まった山梨県上野原の土地について、なぜ、「スポーツ施設建設」という当初の目的を果たせず、区民に多大な負担をかける結果となったのか検証し、二度とこのようなことがないことを確認する。 (表面「幻のスポーツ施設 上野原」をご参照ください。) ●その他 副区長3人制について 地方自治法に元づき、地方自治法の改正の意味と「助役職」がなくなった意義を考えていただきたい。区長を「助ける」「助役」ではなく、トップマネージメント強化ができる区長に次ぐNo.2の「副区長」が新たに設けられたのであり、総務部長の仕事と政策担当部長職をこなすのでは、1人の副区長だけが多忙で逆効果だ。2008年10月24日 補正予算反対討論 中野区によるサンプラザの株取得について4年前、区は2億円の出資でサンプラザ運営を手中に収めることができる新しい枠組みを作った。今回、その枠組がうまく機能しなくなったと言って、区民に対する説明も、理解してもらう時間もなく、区民の税金使うことに反対する。 (表面「サンプラザ株式取得」をご参照ください。) |
|
 |
|
2008年12 月1日 一般質問 -青少年の健全育成について- (1)薬物の乱用防止について 私は常に、子どもたちが犯罪に巻き込まれることがない、犯罪者になることのない社会を考え、いろいろな場面で講師をさせていただいている。 「薬物」は所持した瞬間に「犯罪に巻き込まれ」、その先にあるのは、「犯罪者」への道である。ネット上では「禁止薬物」を含む薬販売のメールが流れ、野放しで入って来る情報を水際で止めるのは難しい。今話題になる大学生の大麻問題、おとなしい真面目な大学生が、「友人」に誘われて興味本位で始めた大麻を、断ろうとしたら、「友人の先輩」から巨額の金を要求されたという話も聞く。知らないうちに暴力団まがいの組織にはまり込んでしまっていた。 学校では「薬物乱用禁止」について教育しているが、「薬物を摂取するとこんなひどい状態になる」「とにかく絶対断ること」という部分の教えだけでは、まだ不十分である。それに加え、ネットなどの情報に惑わされない「判断する教育」、「薬」は必ず「お金」のやり取りであるという、消費者としての「お金の教育」、「友だちだから」と安易に考えない「人間関係の教育」が必要になってきていると思う。 悪い誘いに対して、きっぱり「NO」と言えるようになる。自分の頭で善悪を判断できる。もし困った時は、相談できる大人がいる。これが、若者が「犯罪に巻き込まれない」教育の第一歩になると考える。 (2)(仮称)U18プラザについて 平成21年度設置が決まった「(仮称)のU18プラザ」の具体的な姿が未だに見えてこない。 乳幼児から中高生まで一日約140人が利用する私の地元の「北原児童館」を例に見ても、同じ空間を、設備やソフト面の充実なしに「(仮称)U18プラザ」に変えれば、乳幼児や小学校低学年等はのびのび遊べないのではないかと危惧する。また、年齢で使用時間帯を分けるのでは、中学生が年下の子どもたちに配慮し面倒を見ながら遊ぶ、子どもたちが自ら暗黙のうちに作ったルールや交流が消えてしまう。乳幼児・小学生・中高生、それぞれに使いにくく、且つ、近所に迷惑を掛けてしまう施設になる可能性もある。 キッズ・プラザを持たない今の児童館は、乳幼児・小学生が使い、「南中野」「大和児童館」を「(仮称)U18プラザ」として中高生が使いやすい場所を作るのが良いのではないかと思う。中高生を見守り育てる、しっかりとした人材の確保も大切である。 |
|
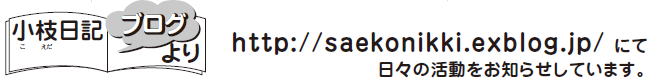 小枝日記 小枝日記 |
|
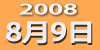
■テコンドーの大会 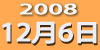
■「老後の不安をのりこえるために」市民の立場から介護保障の道を探るシンポジウム  ◆小枝ネット(ホームページ) http://homepage3.nifty.com/koeda_net/ ◆小枝ネット(ホームページ) http://homepage3.nifty.com/koeda_net/◆小枝日記(ブログ) http://saekonikki.exblog.jp/ |
|
|
|
|
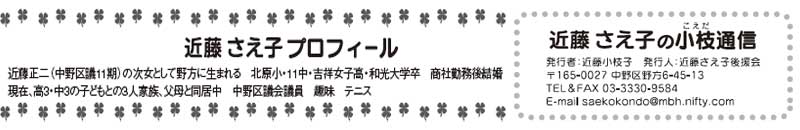 |
※小枝通信Web版は印刷されている小枝通信とデザインその他若干変更しております。
印刷版小枝通信ご希望の方はご連絡いただければ配送いたします。